夕餉の膳
白磁の鉢に、甘海老と白身魚の刺身、烏賊。
身は厚く、艶やかで、まるで今しがたまで泳いでいたような清冽さがあった。

「これは……すばらしい……」
修一郎が、ぬるりと箸を持ち上げる。
「縁の青が、白身の透明感を引き立てて……ああ、この視覚の計算、まるで水墨画のよう……」
「修ちゃん、それもう3回目やわ」
マキは笑いながら、甘海老の尾をつまんだ。
修一郎は、酒が入ると狂ったように同じ話を繰り返す。そして自分で反省会をしてしまう性癖を持っていた。それ自体がひとくくりで彼の性癖なので仕方がない。
「身に艶がある。多分この子、生け簀じゃなくて、近くの港やろな」
一口。甘味が舌に染み込む。
「うん、これは……海の“素肌”や」
ささやくように言って、マキはそっと目を閉じた。
ナナハン君も、箸をとった。
一瞬の逡巡ののち、白身を口に含む。
「……ふむ、これは……」
首を傾けるようにして呟く。
「……なるほど、歯に抵抗がある。鮮度と、包丁の仕事が拮抗していて……これは“緊張”ですね」
「……“緊張”?」
女将の眉がぴくりと動いた。
「ええ……。この白身、寝かせていないのに旨味が滲む。つまり、包丁の刃入れだけで、身に“花”を咲かせた。だが、その刃がやや斜めに入っている。意図的か、技術か――」
「……わたしの庖丁は、斜に入れてございます。ええ、“神経〆”をしていない魚ですから、角度で締めるのです」
女将がぴしりと告げる。
「……やはり。素晴らしい」
ナナハン君は、真剣な顔でうなずいた。
場に、一瞬だけ緊張が走る――が、それも次に運ばれた小皿で和らぐ。
葉のかたちを模した淡い水色の皿の上に、ふっくらとした雪見大福、そして三角に切られた西瓜。
「はー、これ、完璧やん……」
マキが西瓜にちょこんとフォークを刺す。
「わたし、スイカってあんまりよう食べへんのやけど、これは別。冷え方と、切り方と、皿のかたちが気持ちええなあ。お宿の“やさしさ”やわ」
「……皮が口に触れんよう、角度がきっちりついてる。西瓜の“輪郭”が、削ぎ落とされてる」
修一郎は感心して呟いた。
「西瓜が“主”ではなく、“静寂”のような配置だ……」
ナナハン君も、小さく息をついて言う。
「ただ、ひとつ気になるのは……」
「……は?」
女将の声がまた鋭くなる。
「……この大福、どうやらあんこが“こし”ではないですね?」
女将は間を置いて言った。
「……つぶあんにいたしました。“口残り”が、今日の献立にはふさわしいと、わたくしどもは判断しております」
「……なるほど。つぶあん……確かに“夏”の夜に、沈むには丁度良い」
ナナハン君の声は、どこか物思いに沈んでいた。
ヤヴイヌは一言も発することはなかった。これだけの料理を前に、口を開くのは野暮だからだ。いや、むしろ発する暇がなかった。舌は饒舌に語り、その味わいはヤヴイヌの脳を完全に支配した。
押し寄せる波のような情景に、ヤヴイヌの思考はオーヴァーヒート気味だったのだ。
あまりにも強い思いを込められた完璧な料理に寸評をするなど、ほぼ不可能だったのだ。
そこで言葉を発することは、相当な勇気が要求された。さらに、面接官のように女将が立っていて、
この料理が出された時点ですでに我々は裁かれる側だったのだ。
子の料亭の究極まで高められたその技ー。それは狂気と呼ぶにふさわしく、いつの間にか私たちは不思議な世界に足を踏み入れていたようだった。ヤヴイヌはだれか気づいていないかとあたりを見渡す。しかし蛍光ベストはウイスキーを飲んで真っ赤な顔をしているし、女は色目を使っていた。
野人は次こそステーキが出やしないかとそわそわしていた。
そして誰も言葉を発さず、しばし蝉の遠い声と、波の裏返る音だけが流れていた。
面接官
――あの蛍光色、どうにも落ち着かない。
初めて見たときからずっと目障りだった。
なぜ旅先の夕餉に、工事現場の交通整理のようなベストを着て現れるのか。
しかも、正座の姿勢すら妙にきちんとしていて、かえって落ち着かない。
(几帳面っていうのは、悪いことじゃないのよ。でもね、)
「いやあ、このお出汁……舌の裏で輪郭が残るような……ええ、すばらしい。塩の角が一切ありませんね……うん、余韻がある。口腔内に、丁寧な重なりが……」
(……食べ物に“口腔内”って言葉を使うの、やめてほしいのよ)
うれしいのよ。分かってくれてると思えば、ほんとは。
だけど、なんでこう、言葉の使い方ひとつで台無しにできるのかしら。
(あなたの褒め言葉は、だいたい“分析”なの。褒めるなら、もう少し情緒を添えて)
そして気づいた。
彼は食事を「記録」してる。記憶じゃない。
完璧主義者が、味覚のメモを取るように噛んでる――
それは、料理と向き合ってるようで、どこか“心”がない。
(……あれで、アルコールに逃げるんだもの。不思議よね)
彼のポケットには、今日もジャックダニエルの小瓶が見えた。
色女
続いて女将はマキの方にそっと目線を送る。
――この人、きれいやわ。
それが最初の印象だった。
作ったような色気じゃなくて、にじみ出る余裕――
なのに、時折びっくりするほど大胆なことを言う。
「この椀、ええ塩梅やなあ。ふっと香る柚子が、後ろからそっと背中を押すみたいに優しいわ」
(……詩人か何かかしら)
驚いた。でも、嫌いじゃない。
むしろ、こういう“感じる言葉”を出せる人には、料理人としては救われる思いがある。
(あなたの舌は、たぶん本物よ)
だが、それだけに気づいてしまう――
その横に座る、ベストの男と交わす視線。
お互いの言葉を遮ることなく、何度も目を見ては笑う、その仕草。
(……夫婦じゃないわね)
宿をやっていると、すぐに分かる。
ふたりの間にある“近すぎる”距離。
そして時折見せる、後ろめたさの混じった微笑み。
(関わらない。わたしは料理を出すだけ)
けれど彼女が食事のたびに言葉を添えるたび、女将の胸にわずかに灯るものがあった。
……この人だけは、また来てほしいかもしれない。
それに比べてあのレスラーは何なの?
あの大男……。
どこかで見た顔だと思っていた。
だが、あの目の動き、指先の緩さ……料理人ではない。
“食べる側の目”だ。しかも、分かったような口ぶりで、こちらの技に触れてくる。
(包丁の角度にまで口を出すなんて……。何様のつもりかしら)
思わず表情が硬くなりそうになるのを、唇の内側をかみしめて堪えた。
客は神様じゃない。
だけど――この宿は、そういう“お客様”ばかりが来る。
それでも、こしらえた魚は抜群だった。
今朝、あの漁師の庄治が届けてくれたばかりの鯛。
神経締めはせず、敢えて“生きたまま”締めたのは、この身の弾力を活かすためだった。
(あの白身に、緊張があるって……よくもまあ)
あの言葉が誉め言葉であったとしても、素人にいじくられた感覚が残った。
手を握られたような不快さ――
指先を覗き込まれたような、無遠慮な距離感。
(せめて黙って食べてくれればいいのに)
次の皿――水菓子。
器選びにだって、ひと晩かけた。
葉のかたちが季節に沿い、スイカの紅、餅の白、そして皿の淡青が夏の終わりを予感させる。
……だというのに。
(“こしあんじゃないんですね”……?)
その瞬間、女将の手の中で茶器の取っ手が少し軋んだ。
よくぞつぶあんにしておいたものだ――この客のためにではない。
“今日”という一日を感じるには、“ざらり”とした手触りの残る甘味でなければいけなかったのだ。
(あなたに、あの餅の中の“夜のざらつき”が、分かるはずがない)
それでも女将は、笑って膳を下げた。
――この宿は、静かに語る者のための場所。
大声で品評をするための舞台ではない。
(……黙って食え)
心の中で、小さく吐き捨てる。
今日も本当の私を理解できる人は来やしなかった。 続く



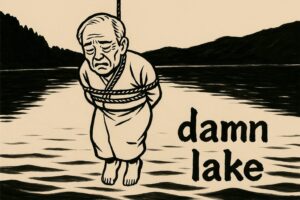





コメント